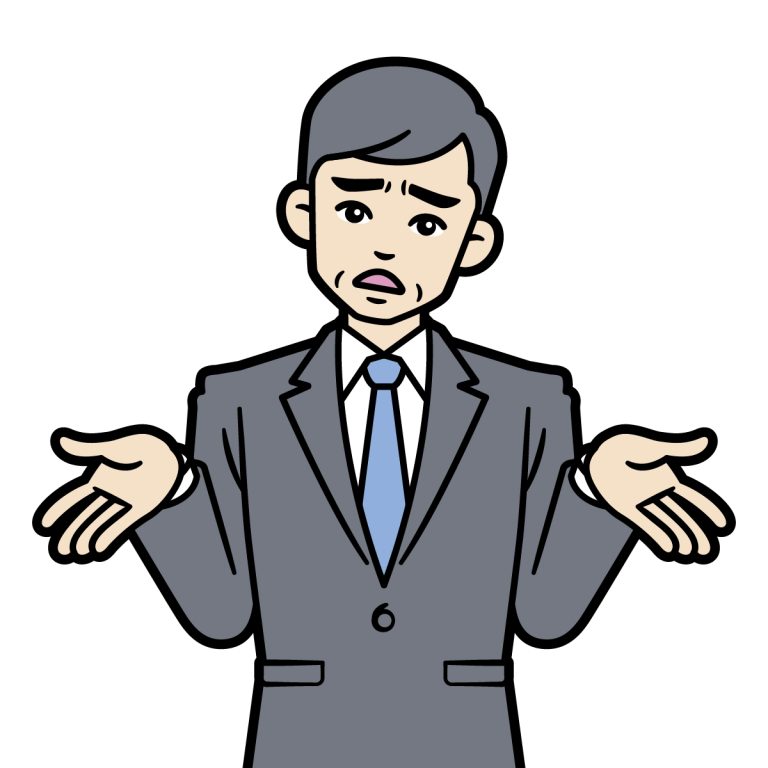部下の育成は、上司にとって避けては通れない重要な役割です。しかし、「仕事ができない部下」に対して、どう接し、どう指導すればよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?指示を出しても思うように動かず、同じミスを繰り返す部下に対して、つい苛立ちを感じてしまうこともあるかもしれません。しかし、感情的に接するだけでは問題は解決せず、部下の成長を妨げてしまう可能性もあります。
では、「仕事ができない部下、どうする?」という問いに対して、どのような指導法や接し方が効果的なのでしょうか。本記事では、部下の課題を正しく把握する方法、効果的な指導のポイント、モチベーションを上げる接し方、そして育成が難しい場合の最終手段まで詳しく解説していきます。部下の成長を促し、チームの生産性を高めるために、ぜひ最後までお読みください。
仕事ができない部下、どうする?まずは原因を正しく把握しよう
仕事ができない部下に対して、つい感情的になってしまったり、「なぜこんな簡単なこともできないのか」と苛立ってしまうことはありませんか?しかし、指導をする前にまず大切なのは、「なぜその部下が仕事ができないのか」という原因を正しく把握することです。適切な対策を取るためには、部下の状況や問題の本質を理解することが欠かせません。本章では、仕事ができない部下の原因を探るためのポイントを詳しく解説していきます。
仕事ができない部下の原因を特定する重要性
仕事ができない理由は人それぞれ異なります。適切な指導を行うためには、表面的なミスや結果だけを見るのではなく、根本的な原因を特定することが重要です。たとえば、「単にやる気がない」と決めつけるのではなく、なぜモチベーションが低いのかを考えることで、適切なアプローチが見えてきます。
仕事ができない部下の原因を探るポイント
部下の仕事がうまくいかない理由を明確にするためには、以下のような視点で原因を探ることが役立ちます。
2-1. 業務の理解不足が原因ではないかを確認する
部下が仕事をこなせない理由の一つとして、そもそも業務内容を十分に理解できていない可能性があります。
- 指示が抽象的すぎて、何をすればいいのか分からない
- 研修やOJTが不十分で、必要な知識やスキルが身についていない
- 業務の優先順位や進め方が分からず、効率的に作業できない
この場合は、業務の進め方を具体的に説明したり、手順書を用意することで改善できる可能性があります。
2-2. コミュニケーション不足による認識のズレがないか確認する
部下の仕事がうまくいかないのは、指示を正しく理解していないことが原因かもしれません。
- 上司の指示が曖昧で、部下がどう行動すべきか迷っている
- 部下が報告や相談をせず、問題を一人で抱え込んでしまっている
- 上司と部下の間で期待される成果や業務のゴールが共有されていない
この場合は、上司が指示をより具体的に伝えることや、部下が気軽に相談できる環境を作ることが解決につながります。
2-3. スキル不足や経験不足が影響していないかを見極める
仕事ができない部下の中には、経験が浅かったり、スキルが足りていないために、仕事のクオリティが上がらない人もいます。
- そもそもその業務をこなすためのスキルが身についていない
- 過去の経験が不足しており、適切な判断ができない
- 基礎的なビジネスマナーや報連相ができていない
この場合は、部下のスキルレベルを把握し、適切な研修や指導を行うことが求められます。
2-4. やる気やモチベーションの低下が関係していないかを考える
部下が仕事をうまくこなせない原因が「能力の問題」ではなく、「やる気の問題」であるケースもあります。
- 仕事に対するモチベーションが低く、積極的に取り組む姿勢が見られない
- 失敗を恐れて行動できず、受け身になっている
- 評価されていないと感じており、仕事への意欲が湧かない
この場合は、部下のモチベーションを高めるためのアプローチが必要になります。(詳しくは次章で解説)
部下の状況に合わせた適切な対応を考える
部下の仕事ができない原因を正しく把握したら、それに応じた適切な対応を考えることが重要です。
- 業務理解不足が原因なら… マニュアルやチェックリストを作成し、業務の流れを明確にする
- コミュニケーション不足が原因なら… こまめな声掛けや進捗確認を行い、相談しやすい環境を作る
- スキル不足が原因なら… OJTや研修を活用し、必要なスキルを伸ばすサポートをする
- モチベーション低下が原因なら… 目標設定やフィードバックを工夫し、やる気を引き出す
原因ごとに適切な対策を講じることで、部下の成長を促し、組織全体の生産性向上につなげることができます。
【まとめ】仕事ができない部下の原因を正しく把握することが指導の第一歩
仕事ができない部下を改善するためには、まず「なぜその部下が仕事をうまくこなせないのか」を正しく把握することが不可欠です。業務理解不足、コミュニケーション不足、スキル不足、モチベーションの低下など、さまざまな原因が考えられるため、決めつけるのではなく、一つずつ丁寧に分析していくことが大切です。原因を明確にすることで、適切な指導方法を選ぶことができ、部下の成長を支援することができます。次の章では、具体的な指導法と伝え方のコツについて詳しく解説していきます。
仕事ができない部下、どうする?効果的な指導法と伝え方のコツ
仕事ができない部下を指導する際、「何度言っても伝わらない」「指示を出しても思うように動いてくれない」と悩んでいませんか?しかし、ただ叱ったり、感情的になったりするだけでは、部下の成長にはつながりません。重要なのは、相手に理解しやすい形で伝え、改善に導くことです。本章では、効果的な指導法と、部下に伝わるコミュニケーションのコツを詳しく解説します。
仕事ができない部下を指導する際の基本姿勢を持つ
効果的な指導を行うためには、まず上司自身が適切な姿勢を持つことが重要です。
1-1. 感情的にならず、冷静に対応することを意識する
- 叱るのではなく、「どうすれば改善できるか」に焦点を当てる
- 一方的に指摘せず、部下の意見や考えも聞く姿勢を持つ
- 落ち着いたトーンで話し、威圧的にならないようにする
感情的な指導では、部下は萎縮するだけで成長につながりません。建設的な話し合いを意識しましょう。
1-2. 部下の成長を促す「サポート役」として接する
- 「教える」のではなく、「一緒に成長する」という意識を持つ
- できていないことばかりに注目せず、少しでも良くなった部分を認める
- 責めるのではなく、「どうすれば良くなるか」を一緒に考える
上司が「敵」ではなく「味方」であると伝わることで、部下も前向きに改善しようとする姿勢が生まれます。
効果的な指導法と伝え方の具体的なコツ
仕事ができない部下に対しては、単に「頑張れ」と言うのではなく、具体的な方法を示しながら指導することが重要です。
2-1. 指示は具体的かつ明確に伝える
- 「ちゃんとやっておいて」ではなく、「〇〇の資料を△△までに仕上げてほしい」と伝える
- 「もっと丁寧に」ではなく、「ミスが起きやすいこの部分をダブルチェックするように」と説明する
- 指示を出す際は、5W1H(誰が、何を、いつまでに、どのように)を意識する
漠然とした指示では、部下が何をすればいいのか分からず、結果としてミスが増えてしまいます。
2-2. フィードバックは「具体例」を交えて伝える
- 「良くない」ではなく、「この部分の説明が不足していたから、次回はここを補足しよう」と指摘する
- 「頑張れ」ではなく、「〇〇の作業はスムーズにできていたから、あとは△△を意識するともっと良くなる」と伝える
- 部下が納得できるように、具体例を示しながら改善策を伝える
フィードバックは、ただ指摘するのではなく、「どうすれば良くなるか」を明確に示すことがポイントです。
2-3. 成果だけでなくプロセスを評価する
- 結果が出なかったとしても、努力した過程や成長した点を認める
- 「結果はまだ出ていないけど、前より作業スピードが上がったね」と声をかける
- 過程を評価することで、部下が次も頑張ろうという意欲を持ちやすくなる
結果だけを求めると、部下はプレッシャーを感じ、指示待ちの姿勢になりがちです。
2-4. 「質問しやすい雰囲気」を作る
- 「何か分からないことがあったら聞いてね」と言うだけでなく、具体的に「〇〇の部分、難しくなかった?」と尋ねる
- 部下が「質問すると怒られるのでは」と思わないよう、普段からフランクに話しかける
- 指導時に「ここまでの説明で分かった?」と確認し、理解度をチェックする
部下が疑問をその場で解決できる環境を整えることで、業務のミスや遅れを減らすことができます。
部下のタイプに合わせた指導の工夫をする
仕事ができない部下にも、タイプによって適切な指導法が異なります。
3-1. 「経験不足」で仕事ができない部下への指導法
- まずは基本的な業務手順をしっかり教える
- 「ここが難しいから、一緒にやってみよう」と寄り添う姿勢を見せる
- いきなり多くの業務を任せるのではなく、少しずつステップアップさせる
経験が浅い部下には、焦らせず、着実にスキルを身につけさせることが重要です。
3-2. 「やる気がない」部下への指導法
- 仕事の意義や役割をしっかり説明し、納得感を持たせる
- 「〇〇ができるようになれば、次のステップに進めるよ」と成長の道筋を示す
- 達成感を感じられるよう、小さな成功体験を積ませる
やる気がない部下には、「やらされている」と思わせない工夫が必要です。
【まとめ】指導は「伝え方」と「接し方」がカギを握る
仕事ができない部下を指導する際は、ただ叱るのではなく、効果的な伝え方と適切な接し方を意識することが大切です。具体的な指示を出し、フィードバックを明確にし、質問しやすい環境を整えることで、部下の成長をサポートできます。また、部下のタイプに合わせた指導法を取り入れることで、より効果的に改善へ導くことが可能です。次の章では、部下のモチベーションを上げる接し方について詳しく解説していきます。
仕事ができない部下、どうする?モチベーションを上げる接し方とは
仕事が思うように進められない部下に対し、適切な指導を行うことは重要ですが、それ以上にモチベーションを上げることが必要不可欠です。モチベーションが低いままでは、どれだけ指導しても成長につながらず、部下自身のやる気も削がれてしまいます。本章では、仕事ができない部下のモチベーションを上げる具体的な接し方について解説します。
部下の努力を認め、小さな成功を積み重ねさせる
仕事ができない部下は、成功体験が少ないことが多く、自信を持てないまま仕事に取り組んでいます。そのため、小さな成功を積み重ねることで、モチベーションを向上させることが大切です。
-
具体的な達成目標を設定する
-
「◯日までにこの作業を終わらせる」「1週間で◯件のタスクを完了させる」など、具体的な目標を設定すると、達成感を得やすくなります。
-
-
できたことをしっかり褒める
-
どんなに小さな成長でも「ここが良くなったね」「前よりスムーズにできているね」とポジティブなフィードバックをすることで、自信を持たせます。
-
否定的な言い方を避け、前向きな表現を心がける
部下のミスや仕事の遅れを指摘する際、厳しく否定するだけではモチベーションを下げるだけになってしまいます。指導の際は、前向きな表現を意識しましょう。
-
ダメ出しではなく改善策を提示する
-
「ここが間違っている」ではなく、「次はこうするともっと良くなるよ」と伝えると、部下は前向きに取り組めます。
-
-
部下の成長の可能性を示す
-
「今はまだできていないけれど、このやり方を覚えればもっと効率的にできるようになるよ」と、未来の成長を想像させるとやる気が湧きます。
-
部下の話をしっかり聞き、意見を尊重する
モチベーションを上げるためには、部下が「自分の意見を聞いてもらえている」と感じることが大切です。上司からの一方的な指導ではなく、部下の話にも耳を傾ける姿勢を持ちましょう。
-
定期的な面談を設ける
-
週に1回でもいいので「仕事で困っていることはないか?」「もっとやりやすい方法はあるか?」と聞く時間を作ることで、部下の不安を軽減できます。
-
-
部下のアイデアを取り入れる
-
「この作業をもっと効率的にする方法はある?」と質問し、部下の意見を活かすことで主体的に考える力を育てます。
-
部下に合った仕事の進め方を工夫する
一人ひとりの適性に合った仕事の進め方を提案することで、モチベーションを高めることができます。
-
業務の細分化と優先順位をつける
-
大きな仕事をいきなり任せるのではなく、細かいタスクに分けて順番をつけると、達成感を得やすくなります。
-
-
部下の得意なことを活かす
-
例えば、資料作成が苦手なら話すことを活かした業務を任せるなど、得意分野を見極めて仕事を割り振ることで、やる気を引き出せます。
-
仕事の意義や目的を明確に伝える
「なぜこの仕事をやるのか?」が分からないと、部下のモチベーションは上がりにくいものです。仕事の意義や目的をしっかり伝えましょう。
-
仕事が組織にどう影響するのかを説明する
-
「この作業が終わると、他の部署の業務がスムーズに進む」など、仕事の価値を伝えると、やりがいを感じやすくなります。
-
-
個人の成長につながることを伝える
-
「このスキルを身につけると、今後のキャリアにも役立つよ」と伝えると、学ぶ意欲が湧きます。
-
信頼関係を築き、安心して働ける環境を作る
部下が「この上司のもとで頑張りたい」と思えるような関係性を築くことが、モチベーション向上につながります。
-
感謝の気持ちを伝える
-
「助かったよ」「ありがとう」と日頃から感謝を伝えることで、部下は「認められている」と感じ、前向きに働けます。
-
-
過度なプレッシャーをかけない
-
失敗を過度に責めると萎縮してしまいます。「失敗しても大丈夫、次に活かせばいい」と伝え、安心して挑戦できる環境を作りましょう。
-
まとめ
仕事ができない部下のモチベーションを上げるためには、「成功体験を積ませる」「前向きなフィードバックをする」「意見を尊重する」「個々に合った業務を任せる」「仕事の意義を伝える」「信頼関係を築く」ことが重要です。指導だけでなく、部下の気持ちに寄り添い、働きやすい環境を整えることで、やる気を引き出し、成長を促すことができます。部下のモチベーションを高めながら、チーム全体の生産性向上を目指していきましょう。
仕事ができない部下、どうする?育成が難しい場合の最終手段
どれだけ丁寧に指導しても、仕事がなかなかできるようにならない部下がいる場合、上司としてどのように対応すべきか悩むことがあります。育成が難しい場合でも、最終手段として取るべきアプローチを冷静に考えることが大切です。本章では、具体的な最終手段を解説していきます。
育成が難しいと判断する基準
部下の成長が見られず、育成が難しいと判断するには、明確な基準を持つことが重要です。以下のポイントを参考に、状況を客観的に見極めましょう。
-
指導の成果が全く見えない:業務を改善する意欲がなく、何度説明してもミスを繰り返す。
-
仕事への姿勢に問題がある:やる気が感じられず、業務の基本ルールを守らない。
-
周囲のサポートがあっても成果が出ない:同僚や他の上司がサポートしても、成果につながらない。
これらの状況が続く場合、次のステップとして具体的な対応策を考えましょう。
具体的な最終手段
業務内容の見直しを行い、適性を再評価する
部下が現在の業務に適性がない可能性も考えられます。以下の点を見直してみましょう。
-
担当業務の変更:苦手な分野を担当している場合、適性のある業務に変更することで改善する可能性があります。
-
役割の明確化:何をすべきかわかっていない場合、役割と期待される成果を明確に伝えましょう。
具体的な改善目標を設定し、期限を決める
漠然とした指導ではなく、具体的な改善目標を設定し、一定期間で評価を行うことが重要です。
-
短期目標の設定:1か月以内に○○を達成するなど、小さな目標を設定。
-
フィードバックを定期的に行う:週ごとに進捗を確認し、改善点を具体的に指摘する。
部下としっかり向き合い、最後のチャンスを与える
最終的に部下としっかり話し合い、今後の姿勢を確認することも大切です。
-
本人の意向を確認する:本当にこの仕事を続けたいのか、別の適性を考えているのかを話し合う。
-
改善の意思を確かめる:意欲がある場合は、最後のチャンスとして再教育の機会を与える。
配置転換や異動を検討する
現在の部署での適応が難しい場合、配置転換や異動を検討することも一つの手段です。
-
適性に合った部署へ異動:適性を見極め、より成果を出せる環境へ移す。
-
他部署と連携して調整:人事部と連携し、適切な異動先を探る。
退職の選択肢も視野に入れる
最後の手段として、退職という選択肢も考えざるを得ない場合があります。
-
本人にとっても適切な選択肢か検討する:無理に仕事を続けさせることが、本人のキャリアに悪影響を及ぼすことも。
-
円満な形での退職をサポートする:可能であれば、次のキャリアへの橋渡しを行う。
まとめ
育成が難しい部下への対応は、慎重に進める必要があります。まずは業務内容の見直しや適性評価を行い、具体的な改善策を提示しましょう。それでも改善が見られない場合は、配置転換や最終的な選択肢として退職の可能性も視野に入れることが求められます。冷静かつ公平に対応し、部下本人にとってもより良い選択を導くことが大切です。
さいごに~仕事ができない部下、どうする?上手な指導法と接し方のコツがわかったら
「仕事ができない部下」にどう対応するかは、上司としての手腕が問われる場面のひとつです。感情的にならず、冷静に原因を分析し、適切な指導とフォローを行うことが、部下の成長につながります。また、一人ひとりの個性や特性に合わせたアプローチを意識することで、部下のモチベーションを高め、より良い成果を引き出せるでしょう。
それでも改善が見られない場合は、育成の方向性を見直し、必要であれば配置転換や業務の見直しも視野に入れることが大切です。上司としての役割は、単に指示を出すだけではなく、部下が成長できる環境を整えることにあります。
今回紹介した指導法や接し方のコツを実践し、部下との関係をより良いものにしていきましょう。